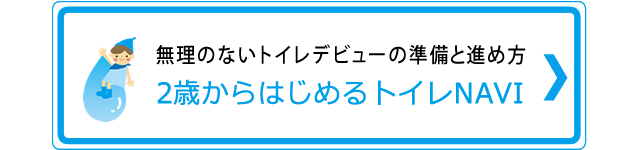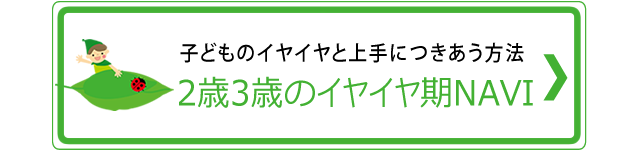ぐずり泣き・夜泣きの予防方法1
例えば、眠る少しまえからお部屋の照明を間接照明にしたり、
授乳中にウトウトしている赤ちゃんを優しくつんつんして起こし、
お腹いっぱいミルクを飲んでから寝かしつけに入る等、
ちょっとした生活習慣の見直しでぐずり・夜泣きを少なくすることができます。
パパ・ママ、赤ちゃんのお互いが楽に生活できるような工夫を紹介します。

ぐずり泣きの予防方法 その1
生活のリズムをつくる
生まれたばかりの赤ちゃんの生活は、
『お腹が空いた』『眠い』等本能にしたがって寝たり起きたりしています。
生後2,3ヶ月後には昼夜の区別がつきはじめ、朝に起きて、寝たり起きたりを繰り返しながら、夜になるとまとめて眠れるようになってきます。
これは、昼間の明るさ・賑やかさと夜間の暗さ・静かさをだんだんと学習していくからです。
つまり、パパママの生活のリズムが赤ちゃんの生活のリズムに大きく関わります。
理想的なリズムは、朝6〜7時に起床、夜は20時〜21時に就寝と言われていますが、実際には難しいですよね。
ですが、リズムを作ることはできるはずです。
朝はできるだけ毎日同じ時間に起き、同じ時間に就寝することを心がけることで、いつもの時間になると自然と起き自然と眠くなる習慣をつけることができます。

できるだけ間接照明を使う
会社や学校の明るいく白い蛍光灯の光とは異なり、夜の飲食店などは柔らかなオレンジの間接照明の光を使っています。柔らかな光の間接照明は気持ちをリラックスさせてくれるからです。
我が家では寝る前の数時間の照明を、蛍光灯から間接照明に切り替えるだけでずいぶんと効果がありました。
豆球にしたり、手頃なスタンド照明を用意することでリラックスしたムードを作りましょう。
優しいリラックスBGMを喜ぶ子もいます。

添い寝してあげる
小さな赤ちゃんを潰してしまわないか心配するパパママもいますが、 パパママの体温を感じられる添い寝は赤ちゃんにとってとても安心するものです。
添い寝しながらおっぱいをくわえさせる「沿い乳」でしか寝ない赤ちゃんもいます。
寝相が極端に悪い場合をのぞいてパパママどちらかだけでも赤ちゃんに添い寝してあげてください。
添い寝していれば、優しくおなかをとんとんしてあげるだけで多少のぐずりなら泣きやませられることも。

しっかりとミルクを飲ませる
おっぱいや哺乳瓶をくわえたことと抱っこされているという安心感から、じゅうぶんにミルクを飲む前についつい眠ってしまう赤ちゃんは少なくはありません。
じゅうぶんなミルクを飲まないまま寝てしまうと、 少し眠った後にまたお腹がすいてすぐに起きてしまいます。
それが続くと睡眠不足になり赤ちゃんの機嫌が悪くなってしまいます。
(特に、消化のよい母乳の赤ちゃんに多いようです。)
安心感から眠りそうになっている場合、お尻のあたりを優しくとんとんと叩いてあげるか、 足の裏をツンツンとして起こしてしっかりと授乳させてあげてください。
※夜中の場合はミルクのために無理に起こさずにそのまま寝かせてあげてください。

夜中の授乳は小さな明かりで
小さな赤ちゃんは、夜中にお腹がすいてミルクを求めます。
それ自体はとても自然なことなのですが、その際に大きな明かりをつけてしまうと赤ちゃんは朝が来たと勘違いして起きようとしてしまいます。
夜中の授乳用に手元に小さな間接照明を用意しておきましょう。
我が家では、充電皿の上に置くだけで簡単に充電できて、ワンスイッチで間接照明・懐中電灯の切り替えのできる照明が大変役に立ちました。
昼間のお昼寝は大丈夫!
少し大きくなって昼寝の回数が減り、夜にまとめて眠れるようになってきた頃、夜しっかりと寝かせたいからとお昼寝を心配するパパママもいますが、小さな子どもにとってお昼寝は大事な時間です。
1〜3時間程度、気持よく寝かせてあげてください。
なかなか昼寝をせずに17時、18時頃から寝てしまう時もありますが、1時間程度は寝かせてあげてください。
もう遅いからと眠い子どもを無理に起こしながらお世話をしてもお互いに大変なだけですよ!
少し眠った後にお風呂、ご飯をすませましょう。
お腹が一杯になったらまた眠くなってきますよ!

胎内音を聞かせる
赤ちゃんが胎内にて聞いていた音を聞かせてあげると落ち着きます。
youtubeのコチラなどが効果がありました。